新任教師に贈る!1年目で潰れないための3つのマインド

この春から教師になるみなさん、おめでとうございます。
苦しかった教員採用試験をくぐり抜け、今は新しく始まる教師人生に希望を膨らませていることでしょう。
子どもはかわいいです。ええ、かわいいですよ。
ですが、子ども相手だからと楽しい毎日が送れるなんて思っていたら、痛いしっぺ返しを食らいます。学校がそんな甘くない世界だということは、新規学卒者の教育・学習支援業における離職率が、大卒で約半分の47.3%という数字が物語っています。
教員の離職率が高いのはなぜ?教員と転職の関係と、転職するときのコツ
本来、教員という仕事はやりがいに満ちたもの。情熱に燃えるのも素晴らしいですが、断言します。
教育に対する熱意だけでは、あなたは数年のうちに潰れます。
この厳しい教育業界を上手く渡って行くための心を、今のうちに作っておきましょう。
子どもに安易に「優しく」するな

あなたは、子どもにとってどんな先生と見られたいですか?
優しい先生?それとも、おもしろい先生?
できれば、「良い先生」として見られたいですね。その通りです。その気持ちはわかりますが、初任の先生は、この「良い先生」の意味を履き違えて学級を崩壊させることが多いです。
子どもは、天使の顔をした「悪魔」である
先ほども述べたとおり、子どもはかわいいです。
そんなかわいい子どもたちを、できれば叱りたくないですよね。子どもにとって身近な存在でありたいですよね。話しやすい先生って思ってほしいですよね。
でも、その思いはここでバッサリ捨てましょう。
子どもは、優しくすればするほど簡単につけ上がります。
叱らない、身近な存在でありたい。それは良いことです。ですが、「優しさ」というのは、子どもの機嫌を取ることではありません。
ダメなことをしたら、本気で叱ってあげなければいけません。馴れ馴れしくしてきたら、目上の人に対する接し方を教えてあげなければなりません。
それをせずに、「かわいそうだから」といった甘い感情でなあなあにしたら、学級の秩序は簡単に崩壊します。子どもたちは、常に「この先生は何をしたら叱るのか」とあなたの出方を伺っているのです。
もし、シメるところでシメなかった場合、「この先生はなんかチョロそうだぞ」と子どもたちは思います。そして、あれこれと、様々な試し行動を行ってきます。これが長く続くと、私語が止まない、立ち歩きが起こるなど、悪い変化が起こり始めます。
気づいたところで、初任の先生がここから学級を修復させるのはほぼ不可能。今更叱ったところで、「先生前はダメって言わなかったじゃん!」と一蹴されて終わりです。
いいですか、子どもは天使なんかじゃありません。天使の顔のお面をかぶった悪魔であることを常に胸に留めておき、様々なサインに気づけるようにアンテナを張っておきましょう。
教員の優しさは、子どものために使うもの
だからといって、いつも眉間にしわを寄せて、怒鳴り散らす教員になりなさいと言っているわけではありません。
そんな先生の下で1年間過ごす子どもの気持ちを考えてみてください。地獄ですよね(笑)
基本的には優しい先生でいいのです。その「優しさ」の使い所さえ間違えなければ。
よく、学校現場では「子どもを褒めましょう」と言います。おそらく、あなたも教育実習などで教わったことでしょう。
褒めることの目的は、基本的には価値づけです。
例えば、いつも目を合わせて話を聞く子がいたとします。
大人から見れば、これは人が話を聞くときの当たり前な礼儀ですが、子どもの中にはそれが「当たり前」のものとしては認識されておらず、無意識にしていることかもしれません。
そのとき、「〇〇さんは、いつも先生の目を見て話を聞いてくれるから、安心してお話しすることができます」と褒めてあげると、自分がした「目を見て話を聞く」という行為には、「相手が安心して話をすることができる」という価値があるのだと、子どもに認識されます。
こうして、自分の行いには価値があると認められた子は、その先もこの行為を進んで行おうとします。そして、周りで聞いていた子も、「目を見て話を聞くことはいいことなんだ。」と思って、それを真似しようとします。もしかしたら、自分も先生に褒めてもらえるかもしれませんからね。
このように褒めることを戦略的に考えると、ちょっと腹黒くも見えますが、結果的には褒めることによって、子どもたちに「人の目を見て話を聞く」という意識を持たせ、より良い方向へ成長させることができるのです。この優しさは、どんどん使っていくべきでしょう。
教員が子どもに対して優しくするのは、あくまで子どもを望ましい方向へ導くため。決して自分が子どもに好かれるために使うものではないことを、肝に銘じておいてください。
先輩の言いなりになるな
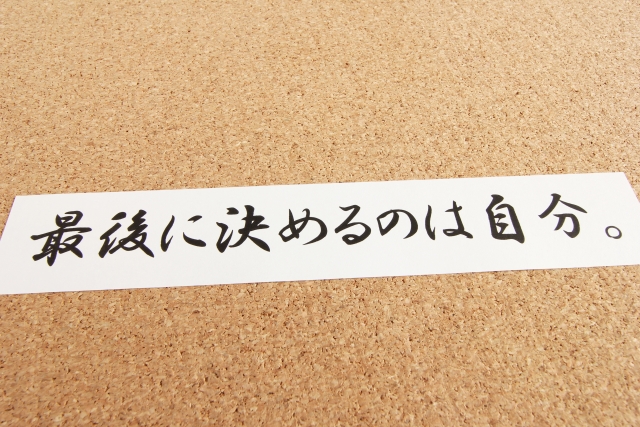
赴任した1年目は、あなたは確実にキャリアでいえば一番下の後輩です。ペーペーのペーです。ですから、学校の先輩方は、職員室や飲みの席などでたくさんのことを教えてくださることでしょう。
学校現場のことについては、あなたの何倍、いや、何百倍以上も先輩の先生方が知っています。ですから、先輩から学ぶということはあなたの成長にとっても、非常に大切なことには変わりありませんので、謙虚に教えを授かりましょう。
しかし、どこの世界でも言えることですが、先輩すべてがすばらしい先輩とは限りません。教員にも「すばらしい先生」がいれば「ダメな先生」だっています。
大事なのは、そのような見極めができる選別眼。自分が「この人みたいな先生になりたい!」と思う先生から積極的に教わることをお勧めします。
先生になったら、よく観察してみてください。大して叱り飛ばさなくてもしっかり学級をまとめている先生もいれば、細かいことにも唾を撒き散らす勢いで怒鳴っている先生もいます。どちらを手本にすれば良いかは、一目瞭然ですね。
1年目は、どの先生が言うことも正しいと思うかもしれません。ですが、その中で「本当にそうかな?」と、常に自分の考えを持ちながら話を聞くと、どの先生の話していることが自分にとって必要かがわかってきます。
ただでさえ多くの仕事に追われる教員という職業。ダメな先生の話を聞くだけ、時間の無駄です。貴重な時間を浪費しないように、あまり関わらないようにしておきましょう(ただし、社交辞令程度の会話は必要ですよ!)。
生意気だと思われるかもしれないからできない?
心配は無用です。だって、あなたが先輩に生意気と思われることと、子どもの成長には何ら関係ないのですから。
心の内では人のせいにしろ

教員になる人は、基本的に正義感、責任感が強いそうです。これを読んでいるあなたもそうかもしれませんね。
そして、精神疾患を患うのも、そのようなタイプの人に多いらしいです。
学級が荒れたら、あなたは「自分の指導力が足りないから」と、自分を責めることでしょう。
周りが慰めても、実際に先輩の先生はきちんと学級をまとめているし、あの子は初めは言うことを聞くいい子だったし…と、自分が悪いと思うような材料を探して、どんどん自分で自分を責めていくのです。
でも、自分を責めて一体何のメリットがあるのでしょうか。それで子どもが変わるならいいですが、ただただ自分が苦しくなるだけで、まさに百害あって一利なしです。
それなら、いっそのこと「あいつが悪い!」と人のせいにする方が気持ちは随分と軽くなりますよ。
冷静に考えてみてください。学級をかき乱している本人は誰ですか?先生ですか?
違いますよね。一部の問題児ですよね。そう、別に先生は悪くありません。むしろ被害者の1人です。
「あいつは自分で自分を変えられないから、自分が何とかしてやろう」というスタンスで臨めば、自責の念からも解放されましょ。
でも、これは自分の心の中に留めておきましょう。表に出してしまったらどうなるかはわかりますよね?笑
ただでさえ、1年目というのは緊張やストレスが溜まりやすいです。無駄な心労を抱え込まないように、どうか自分を責めることは避けてください。
一番大切なのは、先生の心
いかがでしたか。
もしかすると、先生になることに対しての期待を削ぐような記事になってしまったかもしれません。
しかし、健全な子どもを育てたいのであれば、まず教える立場の先生の心が健康であることが条件です。
先生が疲弊した状態では、子どもたちもその姿が自分たちの未来だと思って希望を失ってしまいますし、そんな先生がどんなに前向きな言葉を発しても、何の説得力も持たないでしょう。
子どものためにも、まず先生になるあなたの心を健やかに保つことが大事。この記事がその一助となれば、幸いです。
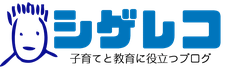




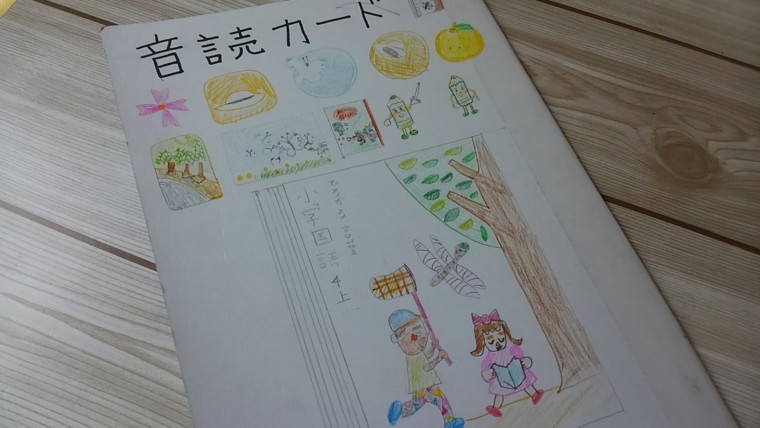




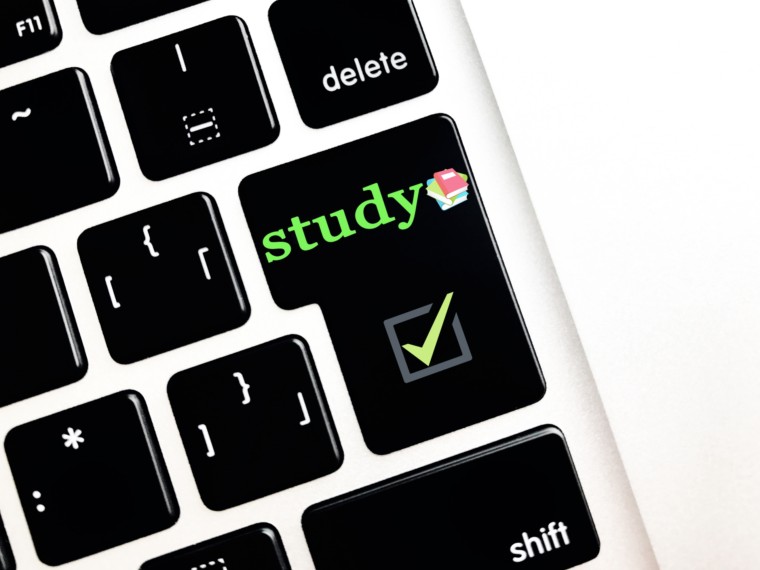
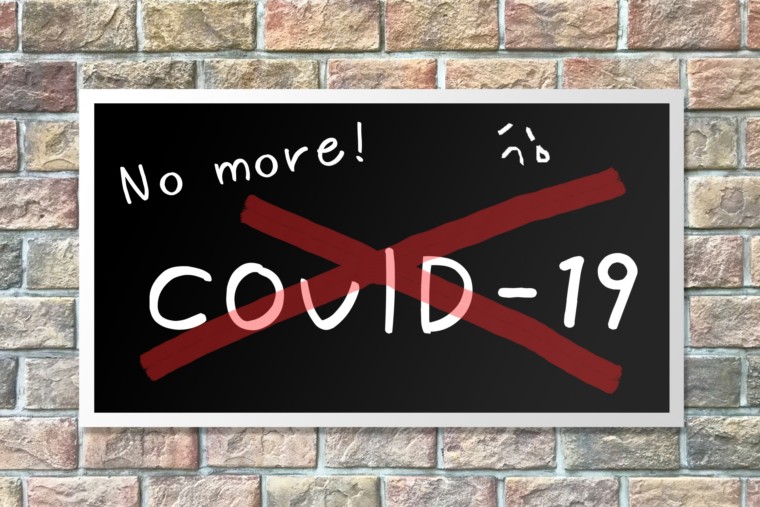





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません